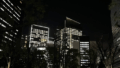ほとんどの国公立受験生が受験し、人生を左右する学力試験である共通テストでは、公平を期すために細心の注意が払われています。カンニング防止や全国一律の試験実施のために厳しい規則が設けられています。その一方で、私はこの共通テストには、システムそのものに圧倒的な欠陥があると感じています。今回は、公平な一発勝負が大前提の共通テストが本当に公平だと言えるのかどうか確認します。
平均点の差を確認する
上は、2025年度の共通テストの科目別平均点の一覧表です。6教科総合型の平均点は6割強となっています。まず感じるのは、科目によって点数にばらつきがあるという点です。ただし、これはあまり大きな問題ではありません。なぜなら国公立大学の入試では受験する必要のある科目が決まっており、まわりのライバルたちもおなじ科目セットを受験して来ているからです(私大の共通テスト利用など、利用する科目に幅がある場合はやはり選択科目によって不公平は生じる)。まあ科目によってウェイトに差が出る(1点の重みに差が出る)のは少し問題ですが、出題側の難しさを考えると許容範囲内でしょう。
しかしよく考えてみると問題があるのは理科と社会です。例えば理系の場合、指定科目が「「物理」「化学」「生物」「地学」の中から2科目」などの条件になっていることがあります。医学部なら、物理化学生物の中から2科目という選択が多いです。ちなみに、共通テストの日程的に、1人が受けられるのは2科目までとなっています。
もう一度平均点を見てみると、物理58.96点、化学45.34点、生物52.21点、地学41.64点とバラツキが出ています。平均点の最大差は物理生物選択者は111.17点(55.585%)、化学地学選択者は86.98点(43.49%)のおよそ24点となります(このセットはあまりない組み合わせではあるが)。
受験者層に差はないか
また、そもそも理科の科目間で受験者層が異なるという問題もあります。もちろん科目は興味や進みたい分野によって選択されるべきですが、一般に物理化学のセットが最もメジャーです。難易度が高いとされる一方で、理工系中心につぶしがききます。次に多いのが化学生物選択で、大学によっては理工系を受験できないこともあるセットです。つまりだいたいの理系受験生は化学はやっていて、物理をやるか生物をやるかの選択なのですが、どうしても、とりあえず物理をやってみて落ちこぼれたら生物をやるというイメージはあります。残念ながら現実でもあります(もちろん生物が好きで特化した人もいる)。平均点に差があるのに加えて、そもそも受験者層の偏差値に差がある可能性があるのです。これは文系の社会科目においても同様です。
コンマ何点差で大学に受かった落ちたという話はよく聞きます。実際僕の周りには共テの受験科目を変更して、コンマ数点差で受かった人がいます。選択した科目によって結果が分かれてしまう現状はいかがなものか…とか思っている今日であります。