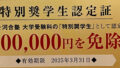2025年度の慶應義塾大学経済学部A方式に現役合格しました。東大の併願だったので対策にかけられる時間は少なかったのですが、短い時間でも効果的に対策できる方法についても書きたいと思います。



慶應経済について
私大の雄、慶應義塾大学ですが、特に経済学部は看板学部ともいわれます。入試には受験科目によって2つのパターンがあり、主に理系向けの英語、数学、小論文(小論文は2027年に廃止予定)のA方式と、文系向けの英語、地理歴史(世界史or日本史)のB方式となっています。A方式は理系の受験生でも受験可能(地歴がない)な私文(レア)なので、東大理系や東工大受験生の滑り止めにもなっていると思われます。もちろん慶應第一志望や文系の併願者もいます。私は東大理系の併願でA方式を受けて合格しました。日程も(たまたまかもしれませんが)慶応理工の次の日だったので受けやすかったです。数学は文系数学です。採点方式について、まず英数のマーク部分のみ採点し、一定の点数に達した者のみ記述部分(英作文、数学の後半、小論文)を採点するという足切りがあります。足切りを突破しないと合格は難しいので、まずは足切り突破が目標になります。
A方式 各科目のコツ
英語
英語は配点が最大となっています。前半はリーディングで補充や文意把握の問題、最終問題はそれまでに読んだ文章をもとに、トピックについて自分の考えを述べるという英作文です。引用などについても指示があります。
2025年のリーディングはまず英文が3問あり、ほとんどが空所補充でした。正直、私のレベルではよくわからない問題もありました。見たことがない単語(難単語?)もちょくちょく出てきます。文意をとれているか注意してください。ほとんどが4択問題です。4問目は日本語リーディングに英語の設問という謎問題です。これらはすべて同一のトピックについて異なる視点から書かれたものです。
第5問の英作文はこのトピックに関して英語で論じるというものです。2025年はまず書きたいテーマ(質問)を一つ選び、それに対して自分の意見を表明、「自分の意見と異なる見解に言及し、それに反論する」「問題文Ⅰ,Ⅱ,ⅢまたはⅣで言及されている見解やことがらを最低一つ取り上げ」「自分の言葉で言い換えて、参照した箇所には著者名と出版年を記す」などと細かい条件が示されています。過去問を見ると、引用の仕方の例が示された年もありますが、2025年は例文はなく、さらに丸写しの引用ではなく言い換えるように指示があります。この指示は昨年からしれっと変化したので、指示は注意深く読み、すべての条件を満たしているかよくよく確認しましょう。うまい引用の仕方について、私は過去問では示されていた例文を1つ丸暗記して本番で使いました。著者名や出版年の示し方で迷う必要がなくなります。英作文の質問は短い英文なので、Ⅰ~Ⅳより先に読んで把握しておくと良いでしょう。その上で、後でⅤの参考にしたい部分に印などをつけながらⅠ~Ⅳを読み進めていきます。ただし、今年と同じ指示ならば文を丸々引用はしないように気を付けてください。英作文はⅠ~Ⅳが読めていないと話にならないです。まずはマーク部分のⅠ~Ⅳで足切り点確保が必要ですし、後でⅤにも使うため、基本的に飛ばすことはできません。だからといって英作文を書ききれないと相当な大幅減点だと思われるので、スピードと正確性を意識して前から順に読んでいくことが基本になります。いかに早く、正確に読んで英作文にたどり着けるかという勝負になります。英作文に特に語数制限はありませんでした。解答用紙がそれなりに大きいので、それなり見合った量は書くべきでしょう。ただし書きすぎると文法、スペルミスも増えやすいですし、そもそも書く時間もそんなにとれません。私は200語ほどを目安にしました。
数学
文系数学で前半は共テみたいなマーク形式で3問、後半は記述式で3問です。もちろん難易度は共テどころではありません。ただし典型問題も多く含まれています。前半マーク部分が足切りの対象になるので、まずは前半で確実にとりにいきましょう。完答までは必要ないですが、完答を目指すくらいでとっておくと安心です。前半はある程度固めてから後半記述式で解けそうな問題を探して解いていきます。後半にも分かりやすい典型問題はあるので簡単なところからとっていきます。すべての問題に向き合おうとすると時間不足ですから、前半は高得点、後半は解けるものを、という姿勢が無難でしょう。
小論文
「小論文」という名前のテストですが、名前のイメージほど理系に厳しいものではなく、解答欄大きめの現代文問題という感じです。東大、京大なら理系でも国語はやっているので、問題ないでしょう。2025年は対比の説明&理由説明(200字)と対比の説明&自分で例を示す(400字)の2問でした。1つの設問に対して書くべきことが2つあることに注意が必要でした。200文字にうまく収まるかが問題ですが、私は下書きしていると時間が足りないと思ったので、前半100字、後半100字に大雑把に分けて順番に書いていきました。配点は大きくないですし、そこまで点差がつくかも微妙なので、書ききること、そして変なことを書かないことを意識すれば大丈夫でしょう。私は本当に自分が思っていることを書くとどんな評価を受けるかわからないと思ったので、ある程度忖度させていただきました。それも小論文のコツかもしれません。
対策について
独特な問題に対応するために何度も繰り返し対策をするのに越したことはないのですが、併願の場合あくまでも第一志望を優先すべきですので、使える時間はあまり多くはありません。それでもあまりナメていると落ちるので、直近1年分は時間を計って解いて、問題の難度や進め方を把握しておきたいです。ただし小論文については自分で採点できないですしどうせ似たテーマは出ないので、真面目に演習する意味は薄いです。問題を眺めましょう。誰かに見てもらえるならやってもいいかもしれません。本番ではまず足切り突破、英作文と小論文を時間内に書ききることが重要です。