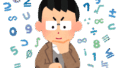(受験生時代に書いた受験記事をいまさら公開します。懐かしい。)
僕が通う東進は2025年度からの共通テストの新たな出題科目、「情報I」に対応すべく、「共通テスト『情報I』体験模試」を開催しています。僕が受験する2025年度は初めての出題になるので過去問が存在しないため、どう勉強すればよいか分からないという不安がある中、共通テスト対応の情報模試を受けられるのはめったにないチャンスです。既に2023年の2月と7月の合わせて二回開催され、もちろん両方受験しました。
テストを受験すると「君だけの診断レポート」で僕だけの診断をしてくれます。自分の成績は恥ずかしいのでもちろん見せませんが、まあ真ん中くらいです。
二回の模試を通して、情報の各分野の中でも特にプログラミング分野の重要性を訴えてきます。確かにプログラミングは知識なし状態では全くと言っていいほど太刀打ちが難しいので、勉強の必要性は高めかもしれません。基礎知識問題は得点源にしたいですね。
ちなみに過去2回とも、東進がやっている東進CodeMonkeyの30ステージ分の体験付きでした。ぼくもやってみましたが、残念ながらステージ2つ目で飽きてしまいました。エンジニアの適性は低いかもしれません。
~ここからは追記記事~
僕が高3生になってからは毎度の共テ模試で情報を受験するようになり、東進と河合を合わせて何回受けとんじゃってくらい情報模試を受けまくりました。情報模試の特徴としては、あまり得点が振れない、対策の仕方がわからない、第4問は毎度同じ手口の問題ばかり、早く帰りたい、といったところです。情報が追加されたことで、受験生の負担はさらに増加しました。いったい30年後の受験生は何十科目受験しているのでしょうか。
初年度ということで模試を作る側も難しかったと思いますが、各社とも少ない試行問題をもとに作っているからか、似たような傾向が形成されていました。
いざ本番共テやで~
驚くほどに知識の必要ない問題ばかり出たという印象でした。模試で出題されていたような純粋な知識問題や、知っておくべきトピックに関する問題はなく、読めばわかってしまうような問題だらけでした。さすがの大手予備校でも予想外なのでは。
初年度ということでまずは簡単な内容が出た可能性はありますが、平均点は情報が明らかに高く、あまりに高すぎるとテストとしての意味を成さないため、次年度以降傾向が変化していく可能性が大いにあります。本当に大変なのは今年ではなく来年以降の受験生なのかもしれません。大事な本番まで傾向がつかめないというのはむちゃくちゃなやり方だと思いますが、他の受験生も同じ条件っちゃ同じ条件なので、自分の目標は確実に達成できるレベルまで能力を高めておくほかありません。