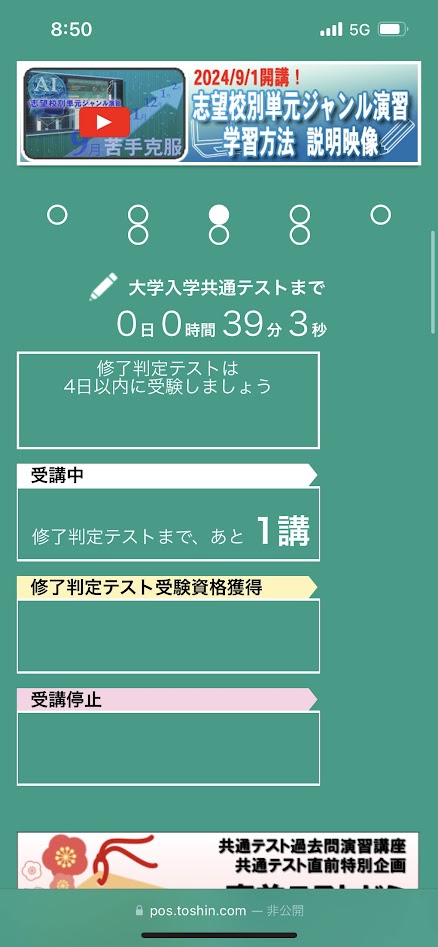共通テスト受験のすぐ翌日、全国の受験生の仕事は「自己採点ののち得点・志望校入力」です。入力した得点は大手の予備校で分析され、数日後にボーダー偏差値や合格可能性が返却されてきます。この結果をもとに、国公立大学の出願先を決めていくことになります。これが共通テストリサーチです。
3社ある
共通テストリサーチを行っているのは主に3社で、河合塾、駿台・ベネッセ、東進です。東進は母数が少ない分粗くなるので、少し厳しめの判定が出るとか出ないとかネットには書いてますが、真偽はよく分かりません。とりあえず最速で返ってきます(この期間の受験生は早く結果が知りたくてウズウズしているので、早いのは嬉しい)。ぼくの学校で入力したのは河合塾と駿台ベネッセです。河合塾や駿台の記述模試とドッキング判定もできます。まあだいぶ前に受けた記述模試なので現役生にとっては信憑性はそんなに高くならないでしょう。
どれくらい当たるか
リサーチが返ってくると日本の受験生は一旦リサーチに夢中になるわけですが、どれほど当たるのでしょうか。データがあるわけではないのですが、僕のまわりを見てると余裕で外れるものだという感じです。そんなに大きくは外さないですが、完全にリサーチを鵜呑みにしなくても…と思います。まあリサーチ以外に何を信じるねんという感じでしょうが。特に今年(2025)の共通テストは少し易化して素点が上がったことで、旧帝大を中心に難関大学を志望校に登録する人が増えたためか、「今年の受験生はチャレンジ志向か!」と騒がれました。また、分析結果には各社である程度バラツキもでます。実際今年の東大の足きり予想は大きく大きく外してる予備校もありました。あえて予備校名は出しませんが。まあ東大とか二次の配点高めの大学ならまだまだ逆転できるので判定を気にする必要性は低いと思いますが(僕の周りにもリサーチE判定からの大逆転複数)、気になるのは私大の共通テスト利用入試の判定です。だって共通テストのみで合否が決まっちゃうんだから。(逆に、リサーチで知っても今更どうしようもないんだけどね。決まっちゃってるから。)
共通テスト利用入試に対する正確さ
共通テスト利用入試では共通テストの得点のみで合否が決するため、かなり正確なリサーチ結果が出るんじゃないかと思います。筆者は早稲田大学の政経経済に出しました。リサーチでのボーダーラインは3社とも「得点率92%」ということで、91%後半だった筆者は大変つらい気持ちになりました。だって3社ともが足並み揃えて言ってるんだから。結局、実際のボーダーラインはツイッターとか見てる限りでは92.5%程度だったようです(確実なボーダーは不明)。
もしあなたが受験生なら
リサーチを眺めても賢くはならないのでさっさと二次試験の勉強に戻りましょう。本当に最後の1か月で結果は変えられます。僕の身近(国立医学部)でもリサーチE判定だったといってる人は本当にいます。今の自分の合格可能性を高めるためにできることをしましょう。それが悔いのない受験です。